「電験二種って難易度が高いって聞くけど、実際どうなの?」
「他の資格と比べてどれくらい難しいんだろう?」
電験二種に興味を持ち、難易度について調べているあなたは、このような疑問をお持ちではありませんか?
電験二種は、電気技術者にとって上位資格であり、取得すればキャリアアップや仕事の幅を広げる上で大きな武器となります。しかし、その難易度の高さから、合格が遠いと感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、電験二種の難易度に焦点を当て、
- 客観的なデータ(合格率など)
- 試験内容の詳細
- 他の資格との比較
- 合格者の声
などを総合的に分析し、電験二種の難易度を徹底的に解き明かします。
記事を読み終えれば、電験二種における難易度の理解が深まり、合格に向けた具体的な対策を立てられるようになるでしょう。
1. 電験二種とは? 難易度を語る前に知っておくべきこと
まず、電験二種がどのような資格であるのか、その概要と取得するメリットを確認しておきましょう。
1.1. 電験二種の概要
電験二種は、正式名称を「第二種電気主任技術者」といい、電気事業法に基づく国家資格です。
主な仕事内容は、事業用電気工作物の保安監督です。具体的には、
- 電圧 17万ボルト未満 の事業用電気工作物(工場、ビル、発電所など)
- 電圧 17万ボルト以上 の事業用電気工作物(一部)
の保安監督を行うことができます。
より高電圧な電気工作物の保安監督を行える電験一種、中小規模の電気工作物を扱える電験三種と比べると、電験二種は中規模から大規模の電気設備を扱え、活躍の場が非常に広い資格と言えます。
1.2. 電験二種を取得するメリット
電験二種を取得するメリットは多岐にわたりますが、主なものとして以下の点が挙げられます。
- キャリアアップ: 電気技術者としての専門性を証明し、昇進や給与アップに繋がりやすい。
- 就職・転職に有利: 求人案件が多く、企業からのニーズも高い。
- 独立・開業: 電気保安法人や個人事業主として独立し、活躍の場を広げられる。
- 社会的信頼性の向上: 専門知識と技術を持つ証明となり、顧客や取引先からの信頼を得やすい。
このように、電験二種は電気技術者としてのキャリアを大きく広げさせる魅力的な資格です。
2. 電験二種の難易度:客観的データから読み解く
では、本題である電験二種の難易度について、客観的なデータ と 試験内容から詳しく見ていきましょう。
2.1. 合格率: 合格率が語る難しさ
電験二種の合格率は、例年10~20%程度で推移しています。
この数値は、国家資格の中でも非常に低い部類に入り、電験二種の難易度の高さを如実に示しています。
同じ電験の試験である電験三種の合格率が10%前後、電験一種が5~10%程度であることを考えると、電験二種は一種と三種の中間程度の合格率ですが、それでも決して簡単な試験ではないことが分かります。
2.2. 試験科目と内容: 広範囲な知識と深い理解が必須
電験二種の試験科目は、「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目です。
それぞれの科目で、大学 電気工学 レベルの専門知識が求められます。
- 理論: 電気回路理論、電子回路理論、電気磁気学、電子 デバイス、情報伝送・処理
- 電力: 発電所・変電所、送電線路・配電線路、電力系統運用、電力応用
- 機械: 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御、情報処理、メカトロニクス、電気材料、電気 化学
- 法規: 電気法規、電気施設管理
試験範囲が非常に広く、各科目の内容も専門的で深い理解が必要となるため、十分な学習時間と効果的な勉強法が欠かせません。
2.3. 試験形式: 計算問題と記述問題への対応力
電験二種の試験は、マークシート形式と記述式を組み合わせた形式で行われます。
- 一次試験(マークシート): 全科目マークシート形式
- 二次試験(記述式): 理論、電力、機械の3科目で記述式問題が出題
特に二次試験では、計算問題に加えて、論述問題も出題されるため、
- 公式や理論の深い理解
- 計算力
- 論理的な記述力
が求められます。単に知識を詰め込むだけでなく、応用力や問題解決能力も必要となる点が、電験二種の難易度を高めている要因の一つと言えるでしょう。
3. 電験二種はどれくらい難しい? 他の資格と比較してみよう
電験二種の難易度をより深く理解するために、他の資格試験と比較してみましょう。
3.1. 電験三種、電験一種との難易度比較
同じ電験である電験三種、電験一種と比較することで、電験二種の位置づけがより明確になります。
| 資格 | 合格率 | 試験範囲 | 難易度イメージ |
|---|---|---|---|
| 電験一種 | 5~10% | 最も広い | 超難関 |
| 電験二種 | 10~20% | 広い | 難関 |
| 電験三種 | 10%前後 | 比較的狭い | 難しい |
合格率からも分かるように、電験一種が最も難易度が高く、次いで電験二種、電験三種という順になります。
電験三種は、電気の基礎知識が中心ですが、電験二種ではより専門的で応用的な知識が求められます。電験一種は、さらに高度な知識と実務経験が必要となり、合格には長年の勉強が必要となる場合もあります。
3.2. 他の電気・エネルギー系資格との難易度比較
電気工事士やエネルギー管理士など、他の電気・エネルギー系資格と比較することで、電験二種の特徴が見えてきます。
| 資格 | 難易度イメージ | 試験内容 |
|---|---|---|
| 電験二種 | 難関 | 電気理論、電力系統、電気機器、法規など、幅広い専門知識 |
| 電気工事士(一種) | 比較的易しい | 配線工事、電気設備の施工に関する知識・技能 |
| エネルギー管理士(電気) | 難しい | 電気利用設備、エネルギー管理に関する専門知識 |
電気工事士は、実務的な技能が中心となるため、試験対策としては暗記と実技練習が中心となります。一方、エネルギー管理士は、エネルギー管理に関する専門知識が求められますが、電験二種ほど試験範囲は広くありません。
このように比較すると、電験二種は、幅広い電気工学の知識を問われる点で、他の電気・エネルギー系資格とは異なる難しさを持っていると言えるでしょう。
4. 合格者の声: 難しかった点、合格のポイント
実際に電験二種に合格した 人々は、試験の何が難しかったと感じ、どのように合格したのでしょうか? 合格者の声から、難易度と合格へのヒントを探りましょう。
4.1. 合格者が語る「難しかった点」
- 試験範囲の広さ: 「4科目とも範囲が広すぎて、どこから手を付ければ良いか分からなかった」(30代男性)
- 計算問題の理解: 「公式を暗記するだけでは解けない、応用的な計算問題に苦労した」(20代男性)
- 記述問題への対策: 「論述問題で、自分の言葉で理論を説明する必要があり、対策に時間がかかった」(40代男性)
- モチベーション維持: 「試験勉強が長期戦になり、途中でモチベーションが下がってしまった」(20代女性)
合格者の声として多く聞かれるのは、試験範囲の広さ、計算問題の理解、記述問題への対策、そしてモチベーション維持の大変さです。これらの点は、電験二種の難易度を象徴していると言えるでしょう。
4.2. 合格者が実践した「合格のポイント」
- 早期からの取り組み: 「合格には1年程度の勉強期間が必要。早めに勉強を始めるべき」(40代男性)
- 計画的な学習: 「科目ごとに学習計画を立て、毎日勉強時間を確保した」(30代男性)
- 問題集を繰り返し解く: 「過去問題集や予想問題集を何度も解き、問題パターンに慣れることが重要」(20代男性)
- 参考書や講習会を活用: 「自分に合った参考書を選び、分からない点は講習会で質問するなど、 積極的に学習を進めた」(20代女性)
- モチベーション維持: 「同じ目標を持つ仲間と励まし合ったり、合格後のビジョンを思い描くことで、モチベーションを維持した」(30代女性)
合格者は、早期の取り組み、計画的な学習、問題集の活用、参考書や講習会の利用など、 各々に合った様々な勉強法を確立し、実践しています。また、モチベーション維持も合格には欠かせない要素であることが分かります。
5. 電験二種 難易度ランキング
これまでの分析を踏まえ、電験二種の難易度をランキング形式で評価してみましょう。
5.1. 総合難易度ランキング
| 順位 | 資格 | 難易度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電験一種 | 超難関 | 合格率が非常に低い、試験範囲が広い、高度な専門知識と実務経験が必要 |
| 2位 | 電験二種 | 難関 | 合格率が低い、試験範囲が広く専門的、計算問題と記述問題への対策が必要、 学習期間が長期化しやすい |
| 3位 | エネルギー管理士(電気) | 難しい | 試験範囲は電験二種より狭いが、エネルギー管理に関する専門知識が必要、合格にはしっかりとした学習が必要 |
| 4位 | 電験三種 | 難しい | 合格率は低い、電気の基礎知識が必要、 学習期間を確保する必要がある |
| 5位 | 電気工事士(一種) | 比較的易しい | 実務技能が中心、試験対策としては暗記と実技練習が中心、 過去問対策すれば合格しやすい |
このランキングは、合格率、試験内容、合格者の声などを総合的に判断したものですが、電験二種が難関資格であることは間違いないと言えるでしょう。
5.2. 科目別 難易度ランキング
電験二種の科目別に難易度を評価してみましょう。
| 順位 | 科目 | 難易度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 機械 | 難しい | パワーエレクトロニクス、自動制御など、 電気工学の幅広い知識が必要、計算問題も複雑 |
| 2位 | 理論 | 難しい | 電気回路理論、電気磁気学など、電気工学の基礎となる難関科目、計算問題も難しい |
| 3位 | 電力 | 普通 | 発電所、送電線路など、比較的イメージしやすい分野、計算問題は高度なものが多い |
| 4位 | 法規 | 比較的易しい | 法令を暗記することが中心、計算問題は少ない、暗記が得意な人には有利 |
科目別に見ると、「機械」と「理論」が難易度が高く、「電力」と「法規」が比較的易しいと感じる人が多いようです。ただし、これは一般的なものであり、得意科目・苦手科目によって感じ方は異なるでしょう。
6. 難易度を乗り越えるのための対策: 合格への道筋
最後に、電験二種の難易度を乗り越え、合格を掴み取るための具体的な対策を解説します。
6.1. 効果的な勉強法
- 自分に合った参考書・問題集を選ぶ: 口コミやレビューを参考に、自分に合った参考書・問題集を見つけましょう。
- 過去問題集を徹底的に活用: 過去問題集は、試験傾向を把握し、実力アップに欠かせないツールです。最低でも過去5年分、できれば10年分以上を繰り返し解きましょう。
- オンライン学習サービスや講習会を利用: 効率的に学習を進めたい場合は、オンライン学習サービスや講習会を活用するのも効果的です。
- スキマ時間を有効的に活用: 通勤時間や休憩時間など、スキマ時間を活用して毎日少しずつ学習時間を確保しましょう。
- ノートやまとめサイトを作成: 学習内容をノートやまとめサイトに整理することで、理解度を深め、復習の密度を高めることができます。
6.2. モチベーション維持のコツ
- 合格後のビジョンを明確にする: 電験二種に合格することで、どのようなキャリアが開けるのか、具体的なビジョンを描きましょう。
- 目標を細分化する: 大きな目標(合格)だけでなく、短期的な目標(今週は〇〇ページまで進めるなど)を設定し、達成感を積み重ねていきましょう。
- 自分を褒める: 目標を達成したり、 昨日より成長を感じられたら、自分を褒めてあげましょう。
- 休憩も大事にする: 集中力が続かないときは、無理せず休憩しましょう。 音楽を聴いたり、散歩に出かけたり、 自分なりのリフレッシュ方法を見つけておきましょう。
6.3. 試験当日 と 試験後 の注意点
- 試験前日: 十分な睡眠を取り、試験会場までの場所を確認しておきましょう。持ち物チェックも忘れずに。
- 試験当日: 時間に余裕を持って試験会場に到着し、深呼吸をして落ち着きましょう。問題用紙が配られたら、全体をざっと見て、時間配分を考えましょう。
- 試験後: 解答速報でチェックし、自己採点してみましょう。二次試験対策が必要な場合は、早めに勉強を開始しましょう。
まとめ: 難易度が高い電験二種、効果的な対策で合格を掴み取ろう!
電験二種は、合格率が低く、試験範囲も広いため、難易度の高い資格と言えます。しかし、 計画的な 学習と効果的な勉強法を実践すれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
この記事で解説した難易度や対策を参考に、自分に合った学習計画を立て、合格に向けて日々努力を続けていきましょう。
あなたの電験二種合格を心から応援しています!
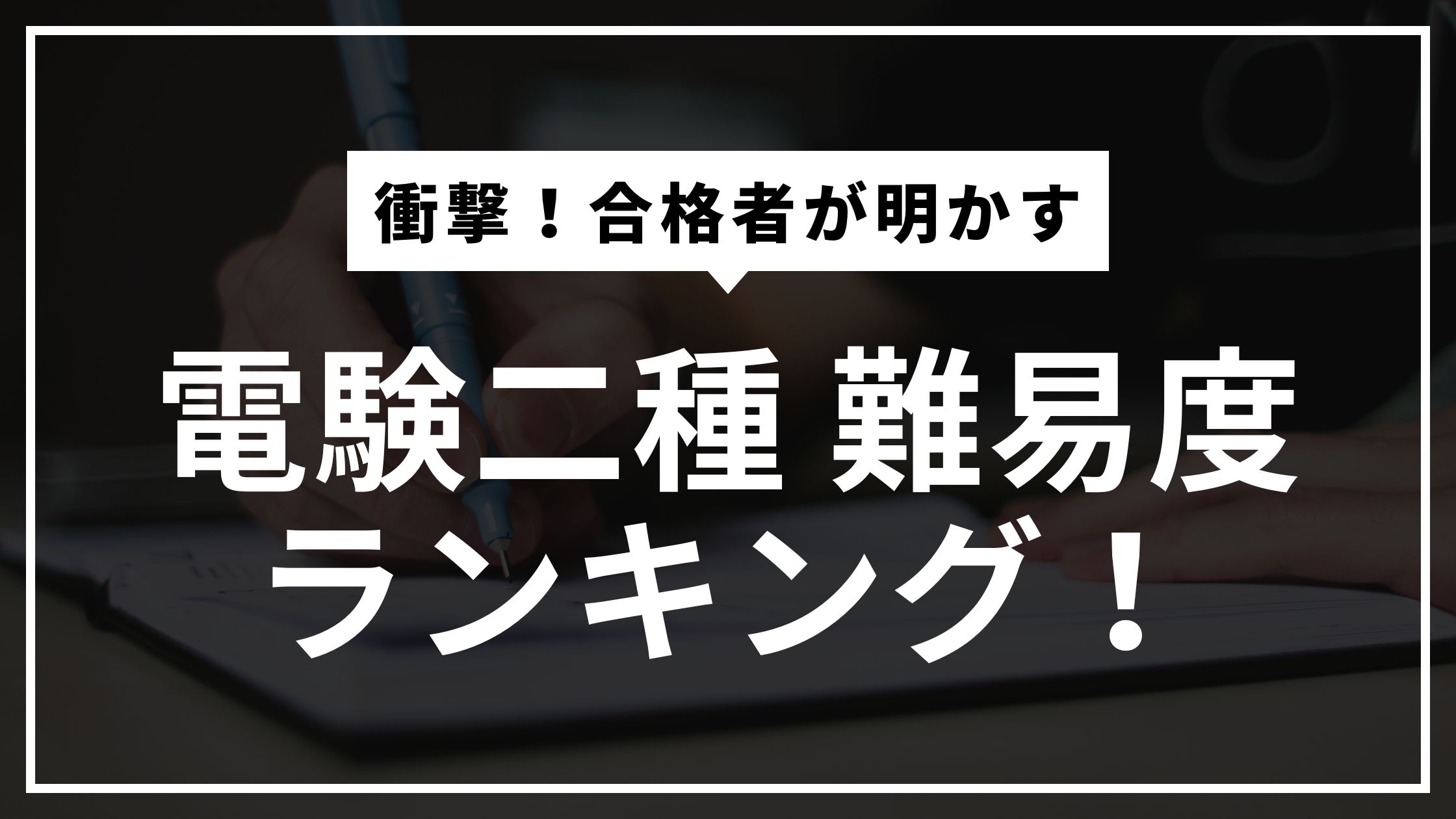

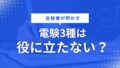

コメント