「電験3種に合格したいけど、効率的な勉強方法がわからない…」 「参考書を読んでも、なかなか理解が進まない…」
この記事は、そんな悩みを抱えるあなたに向けて、電験3種試験に最短で合格するための勉強方法を徹底的に解説します。
電験3種は難易度が高く、独学での合格は容易ではありません。しかし、正しい勉強方法を実践すれば、誰でも合格を掴み取ることができます。
この記事では、
- 合格者の勉強法から学ぶ
- 科目別勉強法
- 段階別勉強法
- 挫折を防ぐ勉強法
など、合格に必要な勉強方法を網羅的に解説します。 この記事を読めば、あなたも最短で電験3種に合格するための具体的な方法がわかり、迷うことなく勉強を進められるようになるでしょう。
第1章:合格者の勉強法に学べ!
まずは、実際に電験3種に合格した人が、どのような勉強方法を実践していたのかを見ていきましょう。合格者の勉強法から、合格のヒントが見つかるはずです。
1-1. 合格者の共通点
多くの合格者に共通する勉強法として、以下の点が挙げられます。
- 計画的な学習: 試験日から逆算し、綿密な学習計画を立て、計画的に学習を進めている。
- 反復学習: 参考書や問題集を何度も繰り返し学習し、知識の定着を図っている。
- 過去問演習: 過去問を分析し、出題傾向を把握した上で、過去問の学習を行っている。
- スキマ時間の活用: 通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を有効活用している。
- 継続的なモチベーション維持: 目標を明確にし、モチベーションを維持しながら行動している。
これらの共通点を参考に、自分自身の勉強法に取り入れていきましょう。
1-2. 合格者Tadaの勉強スケジュール例
わたしが電験3種の勉強頃のスケジュール例をご紹介します。
- 勉強期間: 2年(2年目は2種と並行)
- 1日の勉強時間: 平日1時間、休日2時間
- 勉強の流れ:
- 1~6ヶ月目: 理論科目の参考書を精読し、基礎知識を習得。
- 7~9ヶ月目: 電力科目の参考書を精読し、基礎知識を習得。理論科目の問題集を開始。
- 9~11ヶ月目: 機械科目の参考書を精読し、基礎知識を習得。電力科目の問題集を開始。
- 12ヶ月目: 法規科目の参考書を精読し、基礎知識を習得。4科目の復習も合わせて行う
- ★機械法規合格
- 13~19ヶ月目:理論の試験対策を行う。
- 19~24ヶ月目:電力の試験対策を行う。
これはあくまで一例ですが、計画的に学習を進めるイメージを掴む上で参考になるはずです。 ご自身の学習スタイルや、使える学習時間に合わせて、 スケジュールをカスタマイズしていきましょう。
第2章:科目別勉強法 – 科目の特性に合わせた対策を!
電験3種の4科目は、それぞれ出題傾向や求められる知識が異なります。科目ごとの特性を踏まえ、 効率的な勉強法を実践しましょう。
2-1. 理論科目の勉強法
理論科目は、電気回路、電子回路、電磁気など、電気工学の基礎となる分野を扱います。
- 公式の理解を重視: 公式を暗記するだけでなく、公式がどのような原理に基づいているのか、意味を理解することを重視しましょう。公式の導出過程を理解することも効果的です。
- 図解を活用: 回路図やベクトル図など、図解を積極的に活用し、視覚的に理解を深めましょう。参考書だけでなく、インターネット上の解説動画なども活用できます。
- 計算問題対策: 理論科目は計算問題が中心となります。基本的な計算問題から応用問題まで、問題集や過去問を使って 충분히 演習を行いましょう。
- おすすめ勉強法:
- 参考書を読み込み、基礎知識を習得する。
- 例題や問題集を解き、理解度を確認する。
- 過去問を解き、実戦力を養う。
- 間違えた問題は、参考書や解説を理解し、理解するまで復習する。
2-2. 電力科目の勉強法
電力科目は、発電、変電、送電、配電など、電力系統に関する分野を扱います。
- 系統図を意識: 発電所からユーザーまで、電力がどのように送られるのか、電力系統全体の流れを系統図で理解しましょう。系統図を自分で書いてみるのも効果的です。
- キーワードを整理: 発電方式、送電方式、変電機器など、電力科目特有のキーワードを整理し、用語集などを作成して理解しましょう。
- 暗記と理解のバランス: 電力科目は暗記要素も多いですが、 公式を丸暗記するのではなく、それぞれの用語や設備の役割、仕組みを理解することが重要です。
- おすすめ勉強法:
- 参考書を読み込み、電力系統の基礎知識を習得する。
- 図やイラストを多用した参考書やウェブサイトを活用し、視覚的な理解を深める。
- 問題集や過去問を解き、知識の定着度を確認する。
- 用語集やメモ帳などを活用し、隙間時間にキーワードを暗記する。
2-3. 機械科目の勉強法
機械科目は、電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御など、電気機器とその制御に関する分野を扱います。
- 機器の構造と動作原理を理解: 変圧器、誘導電動機、パワー半導体素子など、主要な電気機器の構造と動作原理をしっかりと理解しましょう。図解や動画教材などを活用するのが効果的です。
- 専門用語に慣れる: 機械科目は専門用語が多く登場します。用語集を作成したり、参考書を読み込んだりすることで、専門用語に慣れていきましょう。
- 理論科目との関連性: 機械科目は理論科目と密接に関連しています。理論科目の知識をしっかりと理解しておくことが、機械科目の理解を深める上で重要です。
- おすすめ勉強法:
- 参考書や動画教材などを活用し、電気機器の構造と動作原理を理解する。
- 問題集や過去問を解き、知識の定着度を確認する。
- シミュレーションソフトなどを活用し、電気機器の動作を体験的に理解する。
- 理論科目の参考書を確認し、関連知識を整理する。
2-4. 法規科目の勉強法
法規科目は、電気法規、電気施設管理など、電気設備の保安に関する法規や技術基準を扱います。
- 条文を中心とした学習: 法規科目は条文が中心となります。参考書だけでなく、電気事業法や電気設備技術基準などの条文を実際に読み、条文に慣れ親しみましょう。
- 条文の理解を深める: 条文をただ暗記するだけでなく、条文がどのような状況を想定しているのか、なぜそのような規定になっているのか、背景にある意味や目的を理解するように努めましょう。
- 過去問で出題傾向を把握: 法規科目は過去問と類似した問題が出題される傾向があります。過去問を徹底して解き、出題頻度の高い条文を中心に暗記しましょう。
- おすすめ勉強法:
- 参考書や条文集を読み込み、電気法規の基礎知識を習得する。
- 過去問を解き、出題傾向と重要条文を把握する。
- 条文集やメモ帳などを活用し、スキマ時間に 重要条文を暗記する。
- 関連法規や技術基準も参照し、理解を深める。
第3章:段階別勉強法 – 基礎から応用へステップアップ!
効果的に学習を進めるためには、 基礎力養成期、応用力養成期、試験対策期という3つの段階に分けて学習することは効果的です。
3-1. 基礎力養成期
最初の段階では、各科目の基礎知識をしっかりと習得することを 목표とします。
- 参考書精読: 各科目の参考書を丁寧に読み込み、基本的な用語、公式、概念などを理解します。
- 理解中心:暗記に偏らず、内容をしっかりと理解することを心がけましょう。不明な点は参考書やインターネット、または先生に質問するなどして、必ず解決するようにしましょう。
- 焦らない: 最初から完璧を目指すのではなく、まずは全体像を把握することを意識しましょう。理解が浅い部分があっても、次の段階に進むうちに理解が深まっていくこともあります。
- 勉強時間の目安: 学習開始から1ヶ月~2ヶ月程度。
3-2. 応用力養成期
基礎知識が身についたら、問題集や過去問を使って応用力を養成する段階に進みます。
- 問題集活用: 基本的な問題集から始め、徐々に難易度を上げていきましょう。問題集を解くことで、知識のアウトプット中心になり、理解が曖昧だった部分が明確になります。
- 解答プロセスを意識: 問題を解く際は、答えを導き出すまでのプロセスを意識しましょう。なぜその公式を使うのか、なぜその解法を選ぶのか、理由を考えながら解くことで、応用力が身につきます。
- 復習を徹底:間違えた問題は、なぜ間違えたのか理由を詳しく分析し、参考書や解説を再確認して理解するまで復習しましょう。間違えた問題をそのままにしないことが、実力向上に繋がります。
- 勉強時間の目安: 基礎力養成期後から2ヶ月~3ヶ月程度。
3-3. 試験対策期
試験直前期は、過去問に集中的に取り組み、試験本番で最大限の実力を発揮できるよう、 最終的な仕上げを行いましょう。
過去問集中学習: 過去5年分、できれば10年分の過去問題を、繰り返し解くことが重要です。過去問を解くことで、試験の出題傾向、時間配分、問題形式を把握し、慣れていくことができます。
時間配分トレーニング : 試験本番と同様の時間配分で過去問を解き、設定時間内に全問題を解答し終える練習 を行いましょう。時間配分を誤ると、たとえ実力があっても不合格となるリスクがあります。
弱点克服: 過去問演習を重ねる中で、自身の弱点が明確化されます。弱点箇所を集中的に復習し、克服することで、合格の可能性を飛躍的に高めることが可能です。
模擬試験の活用: もし可能であれば、模擬試験を受験し、現在の実力を客観的に評価しましょう。模擬試験の結果を分析し、明らかになった弱点補強を集中的に行うことで、より自信をもって試験本番に臨むことができます。
第4章:挫折を防ぐ勉強法 – モチベーション維持のコツ
電験3種の勉強は長期戦になりがちです。途中で挫折しないように、モチベーションを維持するための工夫も重要です。
4-1. 目標を明確にする
「なぜ電験3種に合格したいのか?」を明確にすることで、モチベーションを維持することができます。
- キャリアアップのため
- 給料アップのため
- 自己成長のため
目標を紙に書き出したり、常に目に触れる場所に掲示したりするのも効果的です。
4-2. 勉強仲間を見つける
一人で黙々と勉強するのも良いですが、勉強仲間を見つけることで、モチベーションを高く維持することができます。
- 疑問点を質問し合ったり、教え合ったりすることで、理解が深まります。
- 互いに励まし合い、切磋琢磨することで、モチベーションを維持できます。
- SNSや勉強会などを活用して、勉強仲間を見つけてみましょう。
4-3. 休息日を設ける
毎日絶え間なく勉強を続けると、疲労が蓄積し、集中力の低下を招きます。
週に一度は休息日を設け、心身のリフレッシュを図ることが重要です。 休息日には、趣味に没頭したり、軽い散歩を楽しむなどして、 効果的にストレスを発散させましょう。 そうすることで学習にメリハリが生まれ、結果として学習効率の向上につながります。
4-4. ご褒美を設定する
目標を達成したら、自分にご褒美を与えましょう。
- 合格したら欲しかったものを買う
- 合格したら旅行に行く
- 合格したら美味しいものを食べる
ご褒美を設定することで、モチベーションを高く維持することができます。
おわりに
電験3種合格には、効果的な勉強方法の実践と、継続的な努力が不可欠です。この記事で解説した勉強法を参考に、自分だけの学習計画を立て、合格を掴み取ってください!応援しています!
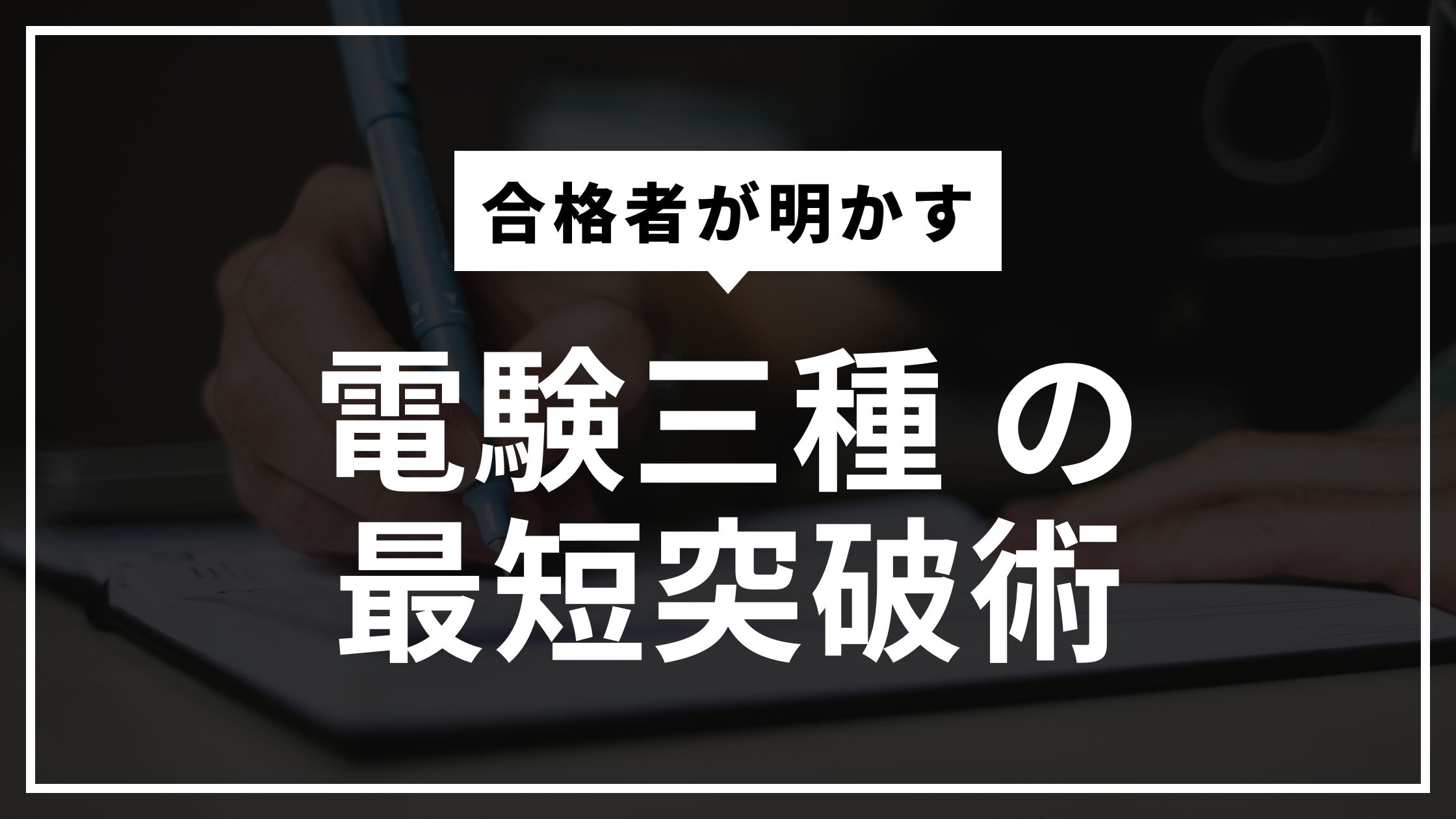


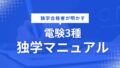
コメント